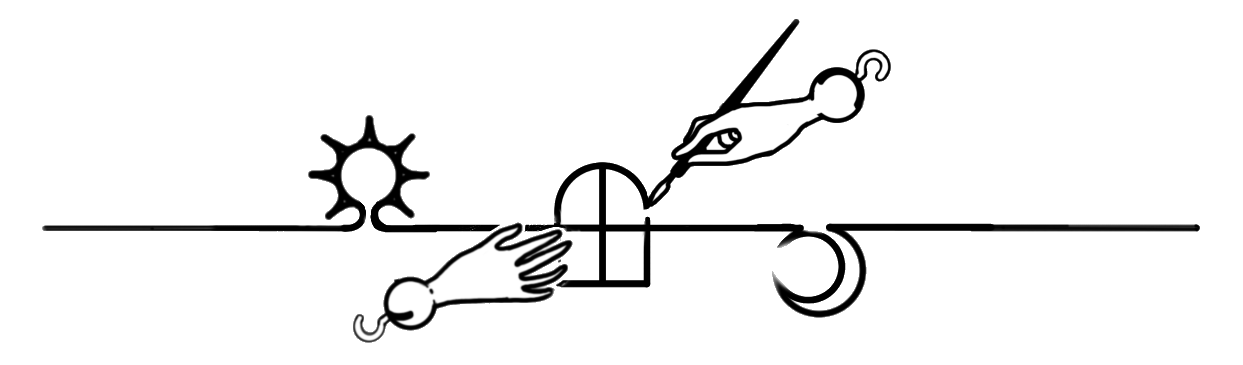黒くてごつごつとした洞窟内には、目が眩むほどの色彩で宝石が埋まっていた。
彼らは陽気な声で笑い、歌い、手を取り合って会話をしては、家族のように繋がっている。
その空洞の、真ん中を歩くのは寒かった。
ここは僕が通るための道ではない。
がらんと、広く、隙間だらけの空間で、温もりの代わりに、冷えた空気が、僕の手を握ってくる。
僕は歌った。
誰のためにでもなく、ただ歌った。
彼らが気づくことはない。
なぜなら僕は、どこにも、存在しないから。
でもきっと、前にも、この道を通った人はそうしたんだ。
そして、これからここに、やってくる人も。
僕らが出会うことはないんだろうな。
それでもきっと、それが僕にとっての家族だ。