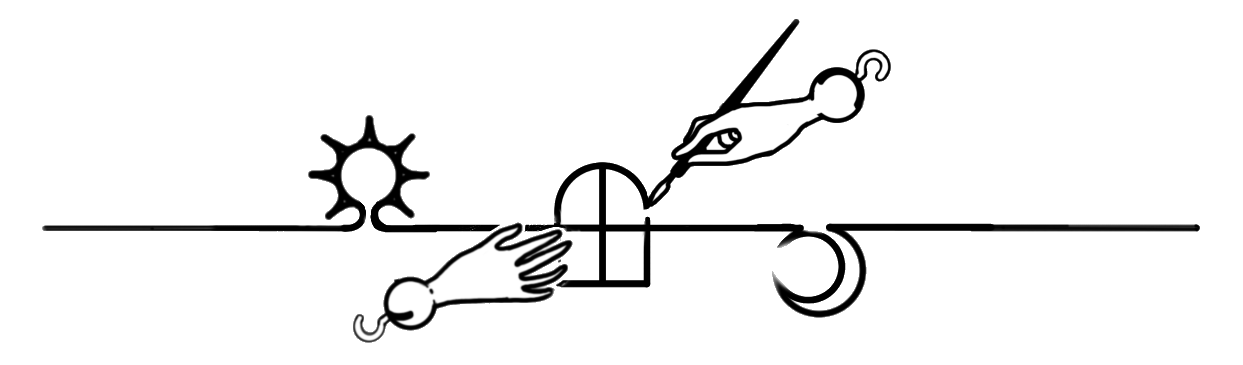あなたは赤が嫌いでした。
でもきっといつか、仲良くなれるのだと、馬鹿なわたしは信じていて、あなたが好きでした。
わたしは朝、透明の空き瓶に身体を傾け、窓辺で揺れていました。
夕方には、寂しげにうつむく、横顔を照らしました。
夜が来て、あなたが大切な人へ贈る手紙を書けば、わたしは封を閉じました。
何も言えなかったけれど、そばにいました。
それからずっと時間が経って、玄関の横にある、ポストの中に1通の手紙が届きます。
慌てたあなたは、机の上のから落ちた本をそのままにして、手紙の封を開けました。
あなたの指には痛みが走って、細い線から小さな粒が吹き出します。
どうか、苦しまないで。
どうか、もう泣かないで。
今ではただひとつだけ、小さなイヤリングが埃をかぶって、机の奥で眠っているだけになりました。
机の上には黄色いガーベラ。
夕方は空色のカーテンを引いて、手紙は書かなくなりました。
愛読書にはグリーンのカバーかけられています。
そして、あなたが痛みで顔を歪めても、隣で誰かが微笑んで、そっと手をかざしました。
それでもわたしはあなたが大切で、どうしようもないほどに、ずっと変わらず赤でした。
今は遠くで、旅をしています。