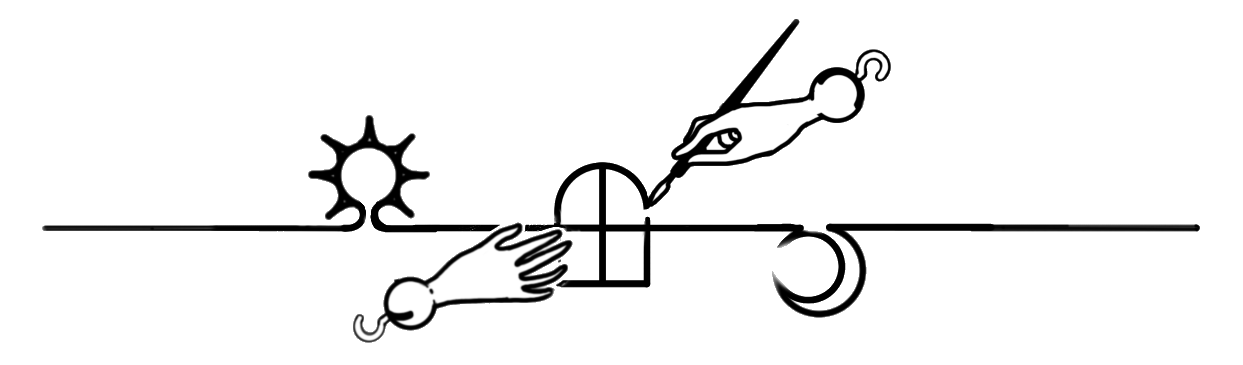「寂しい人に、寄り添う存在でいてほしいんだ。」
たくましく生きている人はいい、君がそんな場所にならなくとも、きっと自分で見出して生きていく、でも寂しい人の側には、いてやってほしいんだ。
想いを託すかの様に、僕に語る。
人は面白いもので、全く別々の、異なる肉体に宿っているにも関わらず、似た様なことを考えていたりする。
「どれほど豊かなものに囲まれたって、人は寂しいんだ。さりげなくていい。1日の中で、安心してその場所に戻れるような、そういう存在になってほしい。」
僕の反応など気にすることなく、街頭演説のように一方的に続く、彼の想いを黙って聞いていた。
熱を込めて語る言葉の奥で、込み上げる何かを堪え、震えているように感じる。
僕だって、そうありたいと思う。
けれど。
現実的なことをすぐに考え出す、僕の癖が始まった。
美しいものばかりとは、とても言い難い世の中で、理想を体現するのは簡単ではない。
優しくあるためには、どうしたって厳しさが必要なのだ。
大きな期待もわかるけれど、僕の幸せはどこに。
言葉を受け止めながら、自分の中で咀嚼していた。
「…ということで、ねぇ聞いていた?」
側で洗い物をしていた彼女への、唐突な問いにより街頭演説は幕を閉じた。
「え?私?!聞いてない。」
明るく笑う彼女の声に、結構いい事言ってたのになぁ、といつもの彼に戻る。
僕も一緒に顔を緩ませ、特別何の返事もしないまま、お開きとなった。
翌日、日向で暖まりながら、この文章を綴る。
太陽の力はすごいもので、こんなに寒い日でも背中がじりじりと焦げそうになる。
「言うだけなら簡単なんだよな…。」
独り言を呟きながら、昨日のことを忘れないように噛み締めていた。